上川町
本田喜市
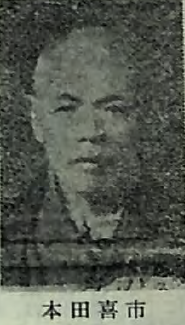
本田喜市(出典①)
石狩川沿いの北村の「草分けの人」を紹介しましたが、今回は石狩川を遡り、源流部の上川町の草分けの人、本田喜市を紹介します。
上川町は、明治30年に設置された愛別村から大正13年に分村しました。しかし、本田喜市の入植は愛別村の開基よりも早く、明治28年です。上川盆地と網走を結ぶ悪名高き国防道路中央道路の開設が明治24年。この道路の利用者のために前後して越路駅逓がつくられます。
駅逓は旅館に郵便局や商店、簡単な行政機能を合わせたもので、北海道の多くのまちは駅逓を中心に発展していきます。上川もこの越路駅逓を中心に発展したいったのでしょうか。以下は『上川町史』(1966)からの引用です。
47歳、5人の子どもとともに入植
本田が入地の頃は、中央道路完工、越路駅逓設置と、越路地域としては重要な交通・通信機関が出来、区画設定も出来ていて相当の便利さであったかと思われる。
しかし、北見通いの国境越えをする者は、当時どれだけあったか。北見・網走とも鉄道もなく、入地開拓も上川中央よりまだ稀薄であった。行き交う人影を見ない日が何日か続くほどであったであろう。そうした地に入地開懇の鍬を下すことには、今日われわれの想像以外のものが多くあったことであろう。
明治28年の初冬、本田は雪を踏んで開墾播種の好機をのがしてはならじと入地したらしい。越路二七線南十番の地に居を構えた。越後地区の区画設定後、その貸付告示があり、さらにその出願が許可になって入地した。
当時、まだ「北海道国有未開地処分法」(明治30年4月1日)の公布前であって、明治19年公布の「北海道払下土地規定」に準拠する時期であった。
本田は、幕末、英国船が浦賀に入港して、ようやく国内が風雲急を台げる嘉永2年2月2日、宮城郡伊具郡佐倉村に出生している。
北海道開拓の意気を燃やして越路に入地したのが47歳の時で、妻女と5人の子供を従えている。構えた住居が中央道路に沿い、しかも越路原野の関門でもあって要衝の地であった。
国境を越え北見に向う人々で、駅逓までゆきつけぬ時はよく一泊を乞う者があったほどであった。また部落内の成功検査で出張して来た道庁・支庁の役人もよく宿泊所にした。
喜市夫妻は以来懸命の努力を重ねた。何としても大地に新開の鍬を振わなければならない。初心に燃えた夫妻は、13~4歳に達した長男、次子を片腕として寸暇を惜しんで耕作に進む。
まず大地をふさぐ立木草むらを伐り開く。伐り開いても伐根までには到底手が及ばない。壌土をさぐりさぐり播種していく。
そば・菜菰・稲黍・大根・麦・馬鈴薯等の自給中心の開拓農業である。土も大小の礫石を交えた癖土。低湿過湿の地もある。
耕して夜に至れば麦・稲黍の夕食。夕食だけではなく主食は麦・稲黍の毎日であった。3人の娘たちは熊・狐の話さえ怖ろしいのに、その姿を見るあけくれにただおののく。
しかし天を仰ぐばかりの視野も、いつか知らぬ間に広がっていく。江差牛山の姿も次第にあらわになってくるほど、立木が伐られる。だが越路峠の方はまだまだ見透しもつかない原野の彼方であった。
実は喜市はこの越路への入地までにひと試練を味わってきている。すなわち入地のこの年早く3月、家族とともに幌向原野十七線に入地して渡道第一の鍬を振った。しかし不幸にして収稚期に秋の水害にあって、初年の目的を壊滅させてしまった。挽回をはかろうとする敵愾心にも似たものがあった。
青年時代、郷里の剣道師範佐藤戸一郎に修業10年を重ね、しかも免許目録を得たほどの身であるから、一層そうした気持ちは強かったのであろう。そんな精神的にも一つの境地を深めていた。
神道信仰に精進して、神道館長総裁神崎一作より教階選叙をうけていたことで知られる。
しかしこと農業に当ってはなかなかであって、入地2、3年というものは、はびこっていた野鼠のため、作物は荒らされる、早い降霜にあうなど思うように行かなかったが、やがて確固たる基盤をきずくのである。
越路の関門二七線に、開拓記念碑を眺めて本田喜市の名を読む時、何人も深い感慨にひたらざるを得ない。

初春の旭ヶ丘から大雪山連峰を望む(出典②)
福井県人と茨城県人が続く
『開拓入門』のコーナーでもお伝えしましたが、入植は団体を組んで行うべきで、単独入植は、開けたまちの近くなどを除いて、すべきではないとしていました。それなのに喜市は47歳という高齢でありながら、単独入植を敢行し、成功させたのです。幌向では手痛い失敗を経験しているにもかかわらず。
中央道路を利用する旅人との触れあいが、わずかに本田の孤独を慰めたのでしょう。それにもまして、若い頃から武道で鍛えた身体と神道信仰が喜市を支えました。
本田の人跡未踏の原野への単独入植というもっとも困難な事業を受け、入植者が続きます。
越路の地は、前記のように本田一家の鍬入れで開拓の緒口がついた。家といえば遥か25町ほど上の越路駅逓の建物があるだけの静寂閑散の越路原野である。
その越路の地にようやく人声を聞き、繁茂する草木の中から煙をみるようになったのは、本田入地の翌年の29年からであって、それからの3、4年間、苦難を覚悟の移住者が続々と入った。北の福井県人と関東の茨城県人とがそれである。
福井県人としては、館源右衛門・五十嵐助右衛門・五十嵐助蔵・内田妙松・森瀬治郎左衛門・伊藤由太夫・内田仁蔵(左右衛門)小倉利右衛門ら、茨城県人としては宮田禎司・小貫平松・植木由松・西木栄作・西木啓次らである。
明治34年5月、これらの人々によって最初の神社「越路神社」が建てられ、いよいよ上川の創建が始まります。
【引用出典】
『上川町史』1966・上川町役場・236-237p
【写真引用出典】
①『上川町史』1966・上川町役場・236p
②上川総合振興局ホーム > 地域創生部 > 地域政策課 > 初春の旭ヶ丘から大雪山連峰を望む2
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/album/view2/window470.htm






















