【岩見沢】岩見沢の士族移住(1)
困窮する廉節義勇の士
岩見沢市の礎となったのは、失業士族の救済策として実施された明治16(1883)年に行われた大規模な士族移住です。岩見沢への入植戸数は277戸、このうち105戸は鳥取県から、山口県は136戸は山口県からでした。それぞれどのような事情があったのでしょうか? まずは鳥取県の事情を探ります。
鳥取藩は、因幡国・伯耆国(現在の鳥取県)を治め、 32万石を有する大藩で、池田家が代々治めてきました。池田家は外様でしたが、第14代池田慶徳は徳川斉昭の実子、幕末の動乱では尊皇と佐幕の間で揺れました。最終的には官軍に付き、戊辰戦争を戦いますが、明治4(1871)年の廃藩置県を免れることができず、家臣も禄を失います。
西日本を代表する藩であっただけに鳥取藩士族の大藩意識は強く、結果的に士族反乱は起こらなかったものの、不穏な空気は充満し、いつ決起があってもおかしくない状態でした。岩見沢への集団移住はこうした不平士族対策として実施されたものです。その経過を『岩見沢市史』『鳥取県史』を中心にして追ってみました。

因幡国 鳥取藩①
■鳥取藩から鳥取県へ
明治4(1871)年7月14日、江戸時代の藩の代わりに1使(開拓使)3府302県が置かれました。このときに鳥取県が誕生しますが、旧藩時代の領域がそのまま新県になった珍しい例でした。
明治9(1876)年の府県統合で3府35県になったとき、鳥取県は島根県に合併されましたが、因幡を中心に鳥取県再建運動が高まり、明治14(1881)年にほぼ旧鳥取藩領域に新しい鳥取県が誕生しました。
さて明治4(1871)年の廃藩置県は数百年続いた封建秩序の崩壊を意味し、地域の動揺は大きかったと思われます。最後の藩主となった池田慶徳は廃藩置県の勅書が出されると、県下の動揺を鎮めるために「県下の四民に諭して」という告諭を発しました。そこで慶徳は
もし心得違い、説諭に従わず、狐疑を抱きて朝命に背き、県令に戻れば、すなわち慶徳の今日の大罪、むしろ身をいるるに地あらんや。汝四民慶徳の為に鎮静して報命せんことを懇請す
と述べました。池田慶徳が東京に移った後、鳥取県政は福岡藩大参事であった河田景与が采配します。

池田慶徳②
■廉節義勇の士風
明治維新により士族と平民の区別は無くなりましたが、額は大幅に減ったものの旧士族には藩主から与えられていた家禄の代わりに明治政府から秩禄が支給されました。秩禄支給の経費は明治新政府の国庫支出の3分の1に達する負担で、これの解消が明治新政府の課題となっていました。
政府は一時金を出すことで秩禄の返還を求めましたが、なかなか成果が上がりません。そこで明治政府は明治9(1876)年に秩禄全廃を断行します。そしてすべての秩禄受給者に年間支給額の5~14年分にあたる額の公債が与えられました。そして5%程度の利子を受け取ることができました。
しかし、もともと家禄に対して元本は大きく削られている上、下級武士になれば利子から受け取る収入もわずかでした。そのため公債を売って商売を始める者も多かったのですが、士族意識を捨てられない者は失敗して没落していきました。
こうして下級士族の困窮は進みますが、鳥取県はとくにその傾向が強かったのです。鳥取県は山がちで平野が少なく、東西に延びた山脈が物資の輸送を困難にしていました。耕地は痩せており、石高は32万石を誇っていましたが、実高はかなり低いと評されていました。
鳥取の初代藩主池田光仲は名君の誉れ高く、武を貴び、廉節義勇の士風を鼓舞しました。そのため藩士は、もっぱら武芸を錬磨し、節操を尊び、卑怯と言われるのを恥、死を恐れない気風を持ち、学問を軽んじ、商売で営利を追うことを潔しとしないことを誇りとしていたのです。
ところが廃藩置県によって家禄を奪われ、学問や商売によって生活をしなければならなくなると、たちまち困窮しました。士族たちは「業を開けば即ち敗れ 社を結べば即ち潰え その財を失い 資力を損じることを少なからず」という状況に陥ったのです。
■士族反乱の季節
こうしたなかで、明治9(1876)年に熊本で神風連の乱、萩の乱、明治10(1877)年に西南戦争が起こると、鳥取士族は激しく動揺しました。鳥取藩士は武闘派で知られていましたから、呼応した動きを政府から警戒され、萩の乱では岡山から巡回隊が派遣されました。
明治10(1877)年に西南戦争が起こると、陸軍卿山県有朋は三条実美に「薩摩に連動するのは鳥取である」との手紙を書き送り、鳥取士族は厳しい監視下に置かれました。
西南戦争中、鳥取士族はまったく動きませんでした。結社をつくり、西郷軍に呼応する動きもありましたが、中止になっています。一方で勤王を説いて薩摩討伐の先鋒になろうという動きもありましたが、警戒された明治政府に退けられました。
鳥取という県は東西に長く、多くの河川で分断された土地で、地域ごとの独立性が強く、藩主という精神的支柱を失うと鳥取士族は分裂し、反乱であれ、恭順であれ、一つの方向にまとまるこを難しくしていったのです。
明治政府に警戒された鳥取藩士は立ち上がりませんでした。しかし、このことは不穏なガスが抜かれることなく蓄積していったことを意味しています。
■鳥取藩の廃止
明治9(1876)年に鳥取県は廃止され、島根県と合併しますが、政庁を失った鳥取の街は灯が消えたように衰微していった『鳥取県史』はいいます。
旧鳥取藩士約6600戸(2万5000人)のうち、4000戸が鳥取に暮らしていたが、当時の鳥取の人口は約6400戸(2万4000人)と推定されているから、その7~8割は士族であった。元来、因伯両国は山陰僻陬の地で、生産性の低い農業に依存していた。その因伯32万石の城下町鳥取は寄生的消費都市で、そこから県庁を取り上げたのでは何も残らない。
施策に対する不平不満は、県都という一つの精神的支えがある間は、江戸の将軍家お膝元という感情と同じく、それに似た優越感で打ち消されていた。しかし、島根県との合併によってこれらの一切は失われた。その上、新しく県都となった松江からは、正に辺境に置かれたことは、格別交通不便な時代にあっては致命的であった。
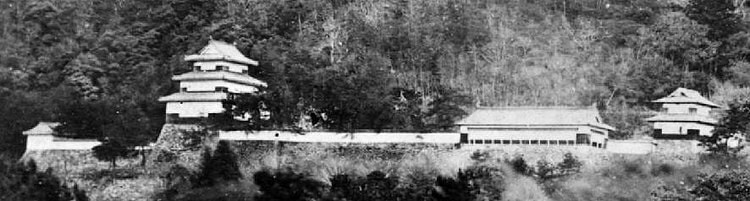
鳥取城二の丸③
県下随一の商都であった鳥取の凋落に合わせて、城下の士族のいよいよ貧窮していきました。『鳥取県史』は、明治13~14年の士族の惨状をこう伝えています。
朝夕糊口に苦しみ飢餓に迫って その惨状は目を覆うばかりであった。そのために、夫は筆墨を売ると称して町村を回り救助を乞い、婦は破れ袋を捧げて憐れみを求め、その有り様はほとんど乞食と同様である。また日給七厘か八厘で機織女工を募集すると、士族の子女が殺到するが、雇い入れて2、3日すると、元気になったりするというのは、極端な栄養不足・飢餓が原因だったのである。
明治10(1877)年の西南戦争で反乱の季節が終わると、士族の反政府エネルギーは自由民権運動に向かいます。組織的な反乱を起こすことがなかった鳥取士族ですが、自由民権運動には積極的に加わりました。
明治6(1873)年に征韓論に破れて下野した板垣退助が、翌明治7(1874)年に土佐で立志社を設立したことが、自由民権運動の先駆けですが、この時、鳥取士族の今井鉄太郎が参画しています。また明治11(1878)年5月15日、大久保利通が東京で刺殺されたとき、6人の刺殺隊のうち2人が鳥取士族でした。このうちの一人、浅井寿篤は自由民権運動の先駆者として知られていました。
こうした空気の中、士族の困窮を背景として鳥取では多くの結社がつくられていきます。そうした一つが北海道移住の原動力になります。
【主要参照文献】
『鳥取県史 近代第2巻 政治篇』1969
『岩見沢市史』1963
『岩見沢百年史』1985
①https://www.shiseki-chikei.com/幕末三百藩-城-陣屋/中国地方の諸藩/鳥取藩-鳥取県/
②https://ja.wikipedia.org/wiki/池田慶徳
③https://ja.wikipedia.org/wiki/鳥取城























