【同時代ライブラリー】 江南哲夫『北海道開拓論概略』(明治15年) ①
北海道を開拓するべきは要務たるや、これ明らかなり
新シリーズを始めます。明治大正期の北海道開拓にまつわる文献を原文で読みます。第1回は江南哲夫(1853-1916)の『北海道開拓論概略』(1882)です。江南は15歳で白虎隊に加わり、慶應義塾から三菱に入りました。明治11(1878)年から3回にわたり渡道し、本書を著しました。明治時代、とくに10年代の士族移民がどのような想いで北海道開拓を志したのか。会津白虎隊の生き残りでもあった江南の書からは、北海道開拓が明治維新の第二幕だったことが伝わります。3回に渡ってお届けします。
■国会図書館ライブリーで読む開拓文献
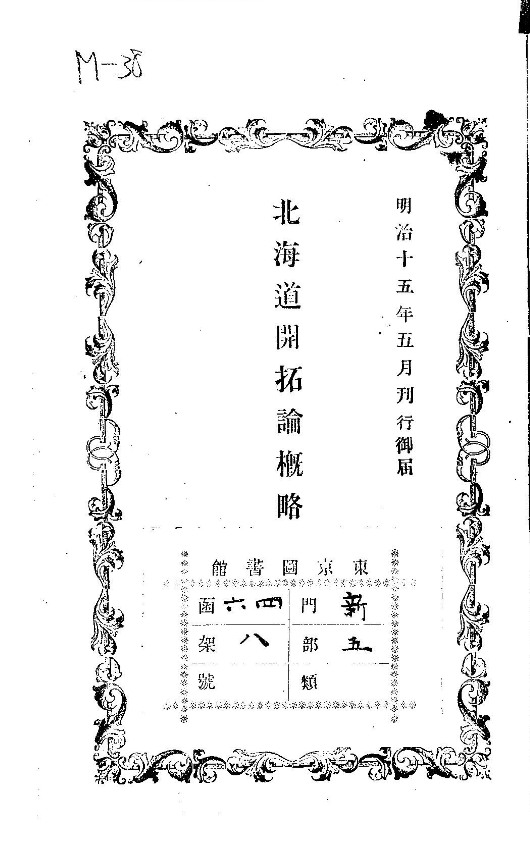
江南哲夫『北海道開拓論概略』 ①
しかし、明治の日本は今よりもはるかに貧しく、人口の大半が貧しさと闘っていました。明治にも貧しさから脱出する手段は数多くあり、そうした中で、なぜ私たちの父祖はあえて極寒の地での戦いを選んだのでしょうか? その疑問に一般的な歴史書は答えてくれません。
私たちが歴史を学ぶというとき、実は○○大学の研究者が書いた書物を読むことだったりします。そうした本を通して歴史を学んだつもりになっても、その歴史とは研究者のフィルターを通して選ばれた「歴史」であり、研究者個人の「見解」であったりします。その研究者の思想に近づくことはできたとしても、歴史の真実に近づいたことにはなりません。そこで大切なのはやはり当時の現資料を読むことです。
これまで「北海道開拓倶楽部」では北海道の歴史を紹介する上で研究者の歴史書に頼らず、歴史の現場に近い市町村史を中心に北海道の歴史を学んできました。それに加えて明治・大正期の北海道開拓に関わる文献を読むことで開拓の歴史を学んでいきたいと考えます。
国立国会図書館は著作権保護期間の終了した明治期の文献をインターネットで公開する

なお採録にあたっては、カタカナを平かなに、旧漢字を現代漢字に、原文にない句読点や改行を入れる、小見出しを付す、一読して理解の難しい漢字を同じ意味の漢字に置き換えるなど、現代人にも読みやすく調整しています(使われていない熟語でも意味が伝わるものはそのままにしています)。
当時の時代の雰囲気を感じていただきたく、改変は最小限に留めていますが、原文は「国立国会図書館デジタルライブラリー」から誰でも無料・無登録でダウンロードできます。ぜひご覧ください。(こちらの解釈の誤りなどありましたらお知らせください)
■江南哲夫 白虎隊の生き残り、岩崎弥太郎の秘書
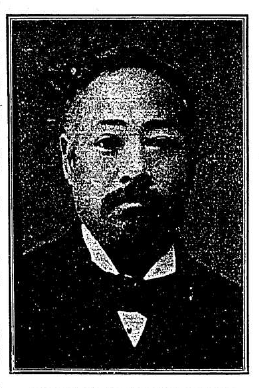
江南哲夫②
卒業後の明治10(1877)年に三菱会社に入社し、書記として社長の岩崎弥太郎に随行しました。明治11(1878)年に北海道開拓を志して三菱を辞職、北海道に渡りました。本書はこの頃に書かれたものです。江南は岩崎弥太郎の秘書となってわずか1年で辞めていますから、江南の北海道開拓への志はかねてより強く、岩崎という明治の傑物に出会うことで、実行を決意したのでしょう。また岩崎弥太郎もそれを後援したものと想われます。しかし、江南の北海道開拓は挫折し、明治17(1884)年、東京に戻り、東京第二十国立銀行に入り、函館支店支配人を振り出しとして後年は実業界で活躍します。
本書は、三菱を辞めた江南哲夫が北海道開拓の同志を集めるために書かれたもので、今回は同書6pからの「管治」を紹介します。会津白虎隊の生き残りでもあった江南の書からは、北海道開拓が明治維新の第二幕だったことが伝わります。
江南哲夫『北海道開拓論概略』
■北海道開墾の最大急務たるは弁をまたざる
本道を区分して11国86郡となし、3県を置おいてこれを分割する。すなわち、函館県は渡島国1カ国、後志胆振国のうち数郡を管治し、札幌圏は石狩、日高、十勝、天塩の4カ国と胆振・後志・北見3国のうち数郡を管治する。根室県は釧路、根室、千島の三カ国と北見のうち数郡を管治する。
全道人口は本籍16万3355人、寄留4万767人。これを明治5(1872)年の人口表と対照するとき、著しい増加を見せているものの、内地人口の各1里四方の平均数によって比較するとき、わずかに70分の1に当たるのみ。
これを読みたる人は、みな北海道の天然地理の概略と管治の区分、人口の疎薄なるとして諒知せん。しかして読者は、はたしていかなる感覚を発するや。
余は自身でこの地を経歴して、その実況を目撃し、しかしてこれを黙止すること忍ばず。すなわいくつか卑見を開陳して、わが邦人に資するところあらんと欲す。
今、わが国、富国強兵の策を講じ、その実をためて内は国基を強固にし、外は国権を万国に拡張せんと欲するのときにあたり、北海道開墾の最大急務たるはもはや弁をまたざるべきなり。
今これを考察するに、天理より、人事より、なかんづく今日わが国の真況よりするも、一つとして今日に適切ならざるなし。
■志士のもっとも痛嘆するところ
そもそも北海道の幅員は、ほとんど欧州中の一小列国に比すべき邦土にして、採取するべきにして、その海陸の大利、ひさしく沈淪(ちりん=埋もれる)して、開発するべきなく宝庫、空しく閉塞して、採取するべきなきは、あに天人の理に反するものにあらざらんや。
けだし、天のその民を生ずるやこれに賦(ふ)するに外物を以て厚生利用の道を開かしむ。ゆえに人類のこの世に棲息するや、生来の遺形を墨守し、弊衣粗食水草を追って漂流するが如き●野の域に停止するは、決して上帝の本旨にあらず。
必ずや吾人の能力を発達し、外物を制御し、これを採取利用して残す所なく働くことなきを期せんのみ。
北海道の如き、数千年来これを文身被髪の種族に委ね、沿岸漁業の利はこれを得るもの多きも、陸産開発の如きはほとんど忘却したるものの如く、しかるはなんぞや維新以来ここに十有余年、官務民業に汲々、開拓に従事したれるも、いまだにその万一を開採利用するに能わず。
ああ、この遺利をして年々消滅せしむること、志士のもっとも痛嘆するところにして、天理に背反するものというべし。いわんや我邦、現時、空手無産の士族数十万の余力あるの時においてや。
■本道開拓は好機会に当たれるもの
北海道を開拓するべきは要務たるや、これ明らかなり。しかし、おおよそ天下の事物、これを処便するにあたり、進退・挙止ひとしく機会あり。その機にあたらざれば、その功労相償うを得ざるのみならず、あるいは全敗をいたすことあり。すなわち本道開墾のごときもまたしかり。
これを事実に徴するに旧幕府の頃、往々にして移民開墾を奨励し、実地に事業を創起せしものにして、功績を奉せし者またわずかなり。(安政年代、新井小一郎幕府に献言して移民したる胆振国長万部の開拓を見よ)。けだし機運の未だ塾せざるために失敗をきせしものならん。
しかるに今日の如き百●ともに興り、民智ようやく進捗するときにして、本道開拓の如きはもっとも好機会に当たれるものと言わざるをえず。
なんぞや今、天下の士民ともに人間自食の大道を解了せしなり。山川、水沢、原野の遺利を開発利用するは人生の義務なることを弁別せしなり。これを人をして争って本地に移住せしむるの容易なるを知らしむるところの現象なり。
かつまたその新境について欧米諸国において積年実験せし、学術技芸を一朝に施用するを得るなり。海陸通運の便利おおいに開けたるより、山岳河海の絶険、至難もこれを消除防避するを得たるなり。加うるに官府の保護奨励優●懇いたるなり。
これをみな昔日に得べからざるところのものにして、今日開拓の好機を得たるとのゆえんの元素なり。
■欧米の得失を鑑みることを得る
おおよそ千百の事、仔細に既住の経験を考察し、その利害得失を推究し、もってこれ将来の事業上に資益するを肝要なりとする。いわんや本道開墾の如き、新規の事業にして、世人のいまだ親しく見聞慣塾せざるもの多きにおいてや。
しかし、幸いにして十年来着手するところの官務民業少なしとせず。札幌、七重の試験場より登別・門別・余市・遊楽部および開進会社などの開拓成績の如きや、後来の起業者のために有益なる証考を示すもの多なりとす。果たしてこの証考なしとせば後進者はあるいは前進者の覆轍を踏まざるをえず。
今やすなわち然らず以上、各所の成敗実験にして、今日の殷鑑たるべきものありて、かつ欧米各地の得失を鑑みることを得るの便あるなり。これまた今日にあらざれば得るを能わずの便益あらざるや。[2]
【引用出典】
[1]北海道博物館『ビジュアル北海道博物館』2016・一般財団法人北海道歴史文化財団・40p
[2]江南哲夫『北海道開拓論概略』1882・6-10p
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801020
①江南哲夫『北海道開拓論概略』1882
②三田商業研究会『慶應義塾出身名流列伝』1909・実業之世界社・712p
③江南哲夫『北海道開拓論概略』1882
























