【旭川・比布】 上川盆地の水稲耕作の発達 ⑤
「道産米百万石」と「客土」の始め
南アジアの亜熱帯地方を原産とする米は、農業者、農業研究者の弛まない努力によってついに北緯43度、上川盆地に広がりました。しかし、自然は甘くなく、大正2年に厳しい試練を農民に与えました。
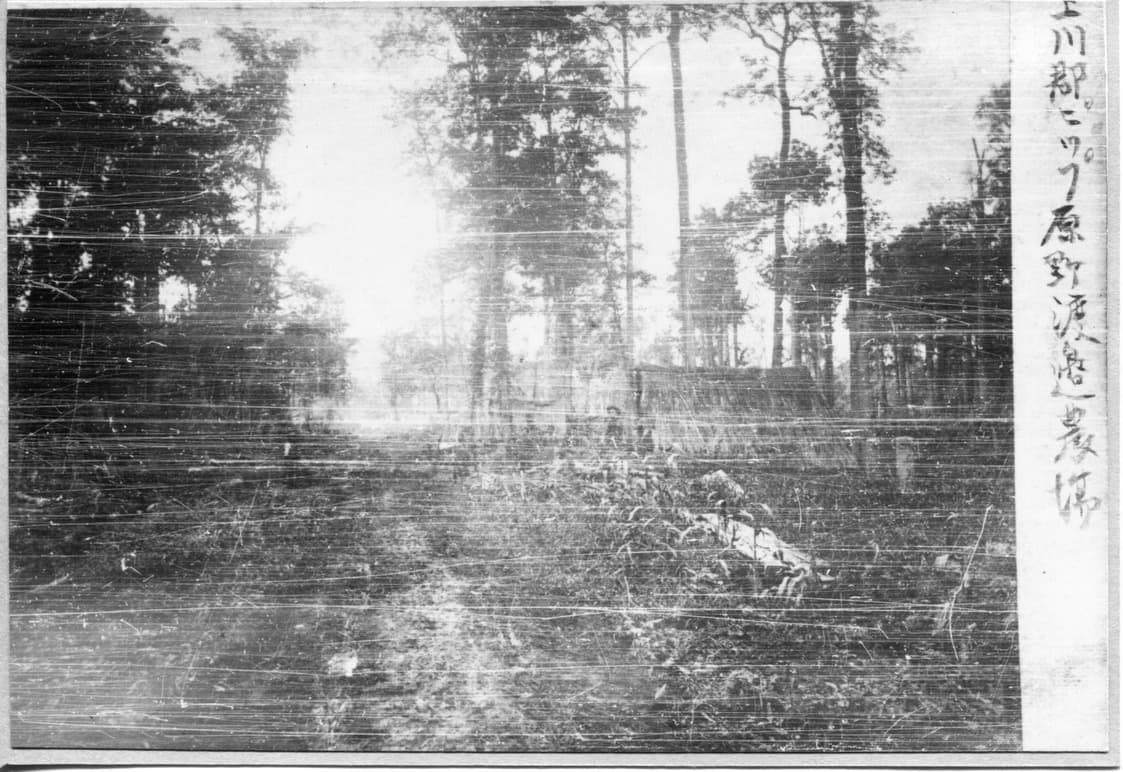
①上川郡ピップ原野渡辺農場, 明治33年以前 : 旭川市図書館
■大正2年の大冷害
北海道の寒地稲作は、上川農事試験場を中心とした品種改良によって大きく前進しました。しかし、大正時代に入って最初の試練を迎えます。大正2(1913)年大冷害の到来です。
上川地方における耕地面積は、明治45(1912)年春において田18534町9反、畑71,647町2反、計90,182町11反に伸長していたが、大正2(1913)年の冷害大凶作によって、その収穫は平年作に比し、水稲は8厘2毛作、大豆は2分5厘作、小豆は1分1厘作という大减収となり、その被害額は約551万円(前年の農産総額は12211万円余であった)に達したのである。[1]
この冷害がどのようなものだったのか、同じ『比布町史』の740p「大正2(1913)年の大凶作とその後の冷害」から紹介します。
この年の上川地方における作况を道庁技師加藤木保次の調査にもとづいて要約すると、5月から9月までの間に平年より高温であったのは5月下旬から6月上旬までの2週間、7月下旬の上半旬、8月上旬の3回で、前後を通じて約30日に過ぎず、他はいずれも例年より低温で、とくに6月中旬から7月上旬にかけての約30日間と、8月中旬から9月中旬に至る約35日間はもっとも陰冷の天気が続き、夏作物はほぼ平年作に近かったが、秋作物は低温による最悪の影響をうけ、これに加えて第一回の結霜は各地とも平年より1~2週間もはやく、旭川周辺では平年よりも20日早い9月14日に初霜があり、そのため大小豆・水稲等の被害がもっとも大きかったのである。[2]
この年は6月を過ぎても気温が上がらず、温暖化が進んだ今では考えられませんが、9月14日には初霜が降るという異常気象でした。このようなかで村民は筆舌に尽くし難い苦難に陥りました。
このような気象条件のもとで、上川地方の罹災農家は18カ町村7342戸(全農家戸数の28.2%) に及び、そのうちとくに救済を要するものは1488戸に達した。
全般的には食糧の欠乏がひどく、多くの農家はヨモギ・フキ・ワラビ等の野草はもちろん、なかには稲わらを蒸してこれを臼でつき「ワラもち」と称して食用に充てるという窮状が各所にみられたのである。
平年作に比べて水稲は7厘6毛作、 大豆は2分3厘作、小豆は9厘作という大减収を示した比布村では、北海道凶作救済会の発足にあわせて「比布村窮民救済金」を組織し、村内一般から寄付義捐金品の募集を行うことにしたものの、この凶作は般家以外の村民にも経済的な打撃を与えたため、救済会の募集運動はきわめて難渋を示していた。[3]
空前の冷害のなかで農民たちは、牛や馬のように稲わらを食べて餓えに耐えたのです。
■改良品種が救った上川農業
苦境に陥った上川・比布村でしたが、寒地稲作の中心地として、先駆的に改良品種を導入したことで最悪の事態を免れたと『比布町史』は言います。
上川地方では平年作に比べて8厘2毛作という大减収ではあったが、坊主・黒毛赤毛等の作付が比較的うまく組合わされていたので、種もみだけはどうにか確保することができ、むしろ他の地方から種もみの供給を求められるという状况で、その価格も石当り24円から26円(この当時の米価は石当り18円20銭であった)という高値を呼び、一部の農家にあっては自家飯米半分も種もみとして販売し、食料には内地米を購入するという現象がみられた。[4]
中山久蔵の「赤毛」から改良された「坊主」の改良品種は、大正2(1913)年の記録的な低温にも耐え、収量こそ減らしたものの、種もみまで全滅するという事態を避けることができました。
翌年、大冷害を生き残った新品種の種もみの評価が高まり、比布町の農家は農家は種もみを販売することで大冷害による減収を補うことができたのでした。
■北海道産米百万石
この大正2(1913)年の大冷害を乗り切ると、天候は安定に向かい、面積・反収とも大きく伸びました。そして第一次世界大戦が勃発すると、欧州の穀倉地帯は戦場となり、世界的な穀物高騰は空前の好景気を北海道にもたらします。さらに前章で紹介した品種改良の進歩が加わり、北海道の米づくりは大きく花開きます。
大正2(1913)年の凶作によって、比布村における水稲の作付面積は翌3年に334町歩も激減したが、この年の反当収収量1石4斗は升2合を記録したことと、第一次世界大戦にともなう好况や土功組合の事業進展に支えられて、大正4(1915)年にはふたたび21町9反歩も作付面積が増加し、さらに反収も1石7斗九升9合という最高を示したことなどから、稲作に対する気運は急速な高まりを見せはじめた。
こうして大正2(1913)年の冷害大凶作をのりこえ伸展してきた本道の稲作は、大正9(1920)年に119万0107石という生産をあげるに至ったので、この年11月23日には北海道会議事堂で「北海道産米百万石」の祝典が開かれ、各地の稲作功労者たちが一堂に会して喜び、そのなかにその苦難の歴史を語りあい、将来の稲発展を希望のなかに語りあった。[5]
北海道の農民は、この好景気によって蓄財した資金を水稲の灌漑設備整備に投資したのです。大戦終結によって麦や豆などの穀物が暴落したこともあって、安定的な産品を求める気持ちと、日本農民としての米への断ちがたい気持ちから、大戦後に稲作は本道の稲作は急拡大しました。そして農業関係者の長年の夢であった「道産米100万石」を達成しました。
なお「北海道産米百万石祝賀会」には、比布村からは安芸兵蔵と内田靜が比布土功組合として選ばれています。この内田靜は北海道開拓史を語る時に落とせない重要人物ですが、改めて紹介します。
■上川農民によって始められた「客土」
さて大正後半からの稲作拡大では、これまで紹介した品種改良のほかに、この頃に始められた「客土」の効果も大きなものがありました。
上川地方は全道の中核地帯として確固たる地位を誇っていたが、これは土功組合の発達や品種改良の進展、あるいは優良農機具の考案、土地改良事業とくに客土事業の開始等に支えられたものといってよかった。
このうち客土事業は明治41(1908)年に多寄村の富生藤吉が泥炭地に粘土を客入して改良する方法を考案し、これが次第に普及しはじめたものである。[6]

②富生藤吉
「客土」は、他所から運び入れた土によって土壌の改良を図ることで、現在でも土壌改良のもっとも基本的な方法になっています。
北海道においてこの「客土」は多寄村(現士別市)の富生藤吉が初めて行ったとしています。この富生藤吉の物語も道民としてぜひ知ってほしいので改めて紹介します。
抑えておきたいのは、品種改良と並んで寒地稲作が広まる契機となった「客土」は、いち開拓農民の発案と努力によって始まったという事実です。
大正13(1924)年4月15日に旭川市で創立総会を開いた「北海道庁管内土功組合連合会」では、6月に入って「泥炭地の改良費(すなわち客土法実施の経費)に対し国庫より補助せられたきこと」を第49帝国議会に請願した結果、翌14年に採択されたうえ、昭和2(1927)年から国庫補助金が交付されることになった。
比布村においては大正10(1921)年ごろから客土事業が行われたといい、さらに北2線4号の道仙伊次郎は、大正9(1920)年から大正12(1923)年にかけて5町歩の耕地整理を行い、これを美用にしたことが伝えられている。[7]
上川の農業者は団結して客土費用の国庫補助を国会に請願して実現させました。上川の農民によって開始された「客土」は、上川の農民によって、寒冷地稲作の一部として広まっていきました。
このようにして上川盆地を起点に北海道の稲作は急拡大しますが、稲はそもそも南方の作物。世界でも希な極寒豪雪の地の稲作に対して農業の神はさらに試練を与えるのです。
【引用出典】
[1][4][5][6][7]『比布町史』1964・434-438p
[2][3]『比布町史』1964・742-743p
①北方資料デジタルライブラリー
https://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/d
②士別市公式サイト
https://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1245638618293/simple/6_J.pdf
























