社史のススメ ①
変わる本州企業の社史づくり
感謝の記念品から使われる戦略社史へ
いつも昔話ばかりしている当サイトですが、生き抜きにたまには〝今の話〟をしてみようと思います。当方は社史などを多く手がける編集者・ライターですが、この仕事、そうある仕事ではない。社史の編集者・ライターだからこそ感じること、考えること。それはひょっとするとみなさまの企業活動のお役に立つかもしれません。「社史のススメ」としてポチポチと書いていきます。開拓の歴史物でなくて申し訳ありませんが、私のなかではつながっています。第1回は社史の現状です。

北海道の企業と本州の企業との大きな違いに「社史」の捉え方があるでしょう。生産に必須な機械から町内会の寄付まで企業活動には優先順位がありますが、本州の企業は社史にかなり高いランクを与えています。その証拠に本州には相当数の社史制作専門の会社があります。
なぜ企業は社史をつくるのか──そうした会社に教えてもらいましょう。まず社史とは何でしょうか? 大阪の社史専門会社「牧歌舎」は「社史の本質(芯)は経営史である」と言い切ります。
社史の本質(芯)は経営史である
牧歌社 https://bokkasha.com/comhistory/
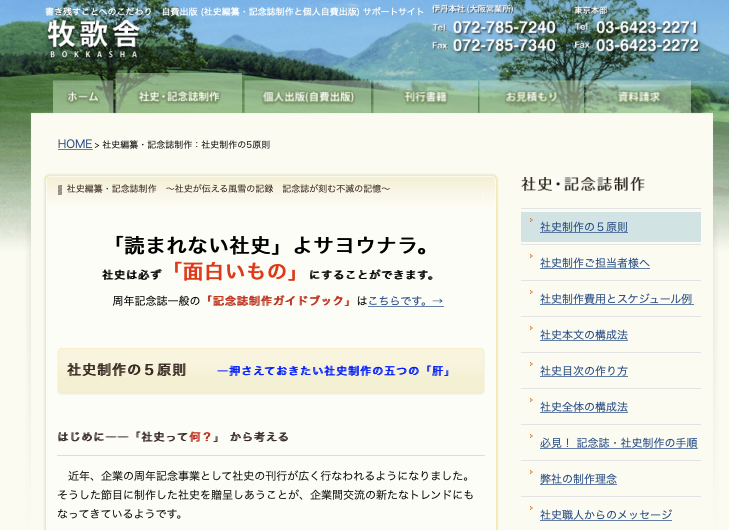
「会社の自分史」というときの「自分」とは何かということを突き詰めて考えた結果、牧歌舎はそれを「経営者」(経営陣)とすることで自分史として必要な脈絡がつながることを確認し、「社史の本質(芯)は経営史である」と皆さんに説明するようになりました。
つまり、社史は単に無限定の「会社の歴史」でなく、創業者がどのような経営目的と経営理念をもって創業し、どのように会社を維持・発展させようとし、時々の経営課題にどのような経営判断を行ってどのような経営戦略を立て、そして結果としての経営状況がどのように推移したかを記した「経営史」として書かれて初めて「社史」になる、という考え方です。
「社史とは経営史」であるという考え方は、大阪本社の社史専門会社・株式会社タイビも最初に掲げているフレーズです。この会社は学校のアルバムづくりから100年前に創業し現在は社史専門にする老舗です。
会社が主語になった会社の自分史
株式会社タイビ https://www.daibi.co.jp/companyhistory.html
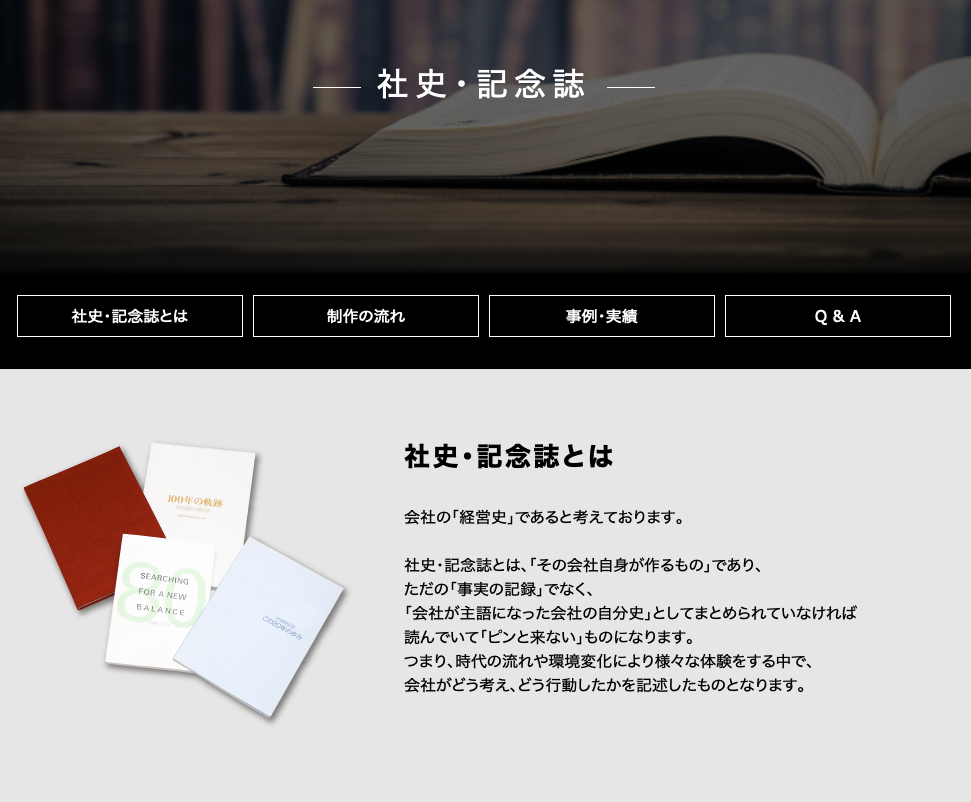
社史・記念誌とは会社の「経営史」であると考えております。
社史・記念誌とは、「その会社自身が作るもの」であり、ただの「事実の記録」でなく、「会社が主語になった会社の自分史」としてまとめられていなければ読んでいて「ピンと来ない」ものになります。つまり、時代の流れや環境変化により様々な体験をする中で、会社がどう考え、どう行動したかを記述したものとなります。
こうした老舗から教わることは、歴史を事実の羅列ではなく、人間のドラマとして捉えようとする姿勢です。
そうすることで企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。これまで1400点以上の社史を制作してきたという東京の株式会社出版文化社は、社史の制作は企業活動に多大なメリットがあると言います。
企業理念や過去の教訓を全社員が共有
株式会社出版文化社『社史の泉』https://www.shashi.jp/shashi/merit.html

社史を作る8つのメリット
◎今後の経営改善、業務改善に役立つ
過去の経験を未来に生かす 「温故知新」。過去の足跡をたどることで得られる教訓を、今後の企業運営に生かすことができます。
◎組織の求心力が高まる
ナレッジマネジメントの一環として、企業理念や過去の教訓を全社員が共有することができます。その結果、組織の求心力が高まります。
◎社員教育のツールになる
自社に対する社員の認識を深め、参画意欲を高揚させることで、社員としての意識の向上に役立てることができます。
◎情報や資料が整理・継承される
周年を機に、社内・外に散逸している資料、記憶・記録などを整理・保存し、次代に効率よく受け継ぐことができます
◎先人、OBの奮闘への感謝の気持ちを忘れない
会社が長い歴史を積み重ねてこられたことへの感謝の気持ちを、会社の内外に表明することができます。
◎周年を祝い、節目を意識してもらえる
節目を形としてしっかりと感じ取ることで、社員の一人ひとりが、自社の歴史の重みと責任を認識できます。また、取引先をはじめ社外にも自社の節目を伝えることができます。
◎企業のイメージづくり・PRになる
会社の発展過程や活動内容を紹介することで、自社のアイデンティティーを社外に伝えることができます。
◎業界、社会への貢献につながる
社史を研究資料として、図書館などに寄贈することで、産業史・経営史・郷土史などの学問的資料として継承することができます。貴重な産業・企業の研究資料として御社の名前が受け継がれます。
すなわち「歴史」はさまざまな分野に活用できる経営資源だというのです。
こうしたことから企業は「社史」を通して積極的に歴史を企業活動に取り入れるようになってきました。それを受けて「社史」の姿も今大きく変わってきていると日本ビジネスアート株式会社『社史の教科書』いいます。
同社は「社史を単に歴史を記録するツールではなく、企業価値を高める実用的ツールとすることを目的として、国の内外で発行されるさまざまな社史を収集・研究し、200社以上の社史制作に参加してきました」という東京の企業です。
使われる/読まれる戦略的社史
日本ビジネスアート株式会社『社史の教科書』https://shashi-kyokasho.com

しかし現在社史のトレンドは、「保管される」される」社史・周年史から、「使われる」「読まれる」戦略的な社史・周年史へとシフトしています。社史・周年史をもっと多くの人に読まれるものにしたい、と考える企業が増えているのです。「使われる/読まれる戦略的社史」とは?
例えば、あるメーカーの事例をご紹介します。
創業者一族以外から新たな経営者を迎えることになったA社。創業のDNAやこれまでの経営判断の根拠を、社内に理解・浸透させる必要性を感じ、社史を社員向けの教育研修ツールとして役立てられるように制作した。結果、新入社員研修の一環として社史を教科書としたDNAインプットの講義を実施するだけでなく、社員がお客様とのやり取りなどで会社のバイブル的に活用したり、復刻版商品などの企画や採用ムービーの参考資料として利用されている。
駆け足で本州の社史を巡る事情を紹介してきましたが、本州の企業では「歴史」に対する受け止め方が大きく変わってきていると思われないでしょうか。
イタリアの歴史学者ベネデット・クローチェの「すべての歴史は現代史である」という言葉があります。すなわち、歴史は過去の骨董品ではなく、現代を生き抜き、未来を拓くための資源──ということです。
まさに本州の社史はその方向に向かって進歩しています。























