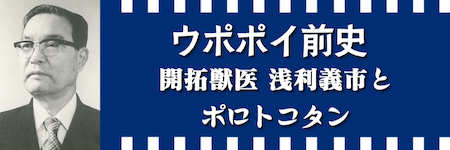[北見]昭和29年 古老炉辺談話
北光社移民団の生き証人が語る開拓の真実 (中)
小雀いずくんぞ大鵬の志を知らんや──と大変な情熱を抱いて北海道に上陸した北光社移民団の人々も、入植地に着き、どこまでも続く鬱蒼とした原生林を前にして絶望的な気持ちに襲われました。それでも後には引けません。明治30(1897)年5月、その日から開墾の日々が始まります。前日に続き、昭和32(1957)年発刊の旧「北見市史」の『古老を囲んでの炉辺談話』による北光社移民団生き証人の証言、クンネップ原野開拓編です。
入植者の苦闘
それから幾日かしてこの北光社ヘー同がたどり着き、やっと心が落ち着いて来た。
この大自然と取り組んで、あくまでやりぬくぞ──という気持が湧き上がった。ここが夢に描いた移住の地、憧憬の地であったのだから。

北見市美里に入植者した開拓者の生活①
疲れを休める暇もなく、すぐ入るべき家を造らねばならぬ。2間(3.63m)に3間(5.45m)の掘立小屋、屋根も壁も野草や木の皮でふいたおがみ小屋同様のもので、大きな鋸(のこ)で挽いた板や割板を使用したのは、秋も大部寒くなってからのことである。
出発のときは多少でも開墾地のあるところという条件であったが、来てみればまったくの草原と密林で、その困苦はひととおりではない。1抱えも2抱えもある木を倒す経験のない者にはこの仕事も容易なものでなく、切り倒された木は枝とともに積み重ねて火をつけ夜どおし燃やした。夜空を赤くそめてあちこちで盛んに燃えさかる風景は、淋しい開拓地を活気づけ人々を興奮させた。
開墾の敵は木だけではなかった。網の目のように根を沃る熊笹もまた開拓者を泣かせた。鍬といっても600匁(2.25kg)もある唐鍬1丁だけ。手の豆はつぎつぎと破れ、血がにじみ、身体は綿のように疲れる。それでも夢中になって働き続けた。
北光社移民として8割開けば大成功とのことで、各戸とも3分の1を開けば所有権を渡す約束である。出発する時に生活代として金100円也(※384万6154円)を渡されたが、1人分の旅費が9円(※34万6154円)、夫婦で18円(※69万2308円)差し引かれ、その残金で食糧の用意、井戸掘り賃、小屋掛け代とかかるので、着いてまもなく1銭もなくなった。
事務所には日用品は売ってはいるが、貴重な品々で、金のない移住民には高根の花であり、どうにもならず、食うことが何よりの先決問題だった。
当時、麦、トウモロコシの計画は全くなく、株間と株間にいくらか播いた程度で、生活苦をしのぐべく馬鈴署を少しばかりと、ソバを少々道路の近くに植えてその成長を願ったが、草原は土地が固くて容易でなく、木のあるところは反当り70俵も取れたが、縞鼠がたくさんいてどうすることも出来ず、やむなく弓を作つて射って征伐したものである。
食糧に欠乏すれば、野生のものをとって、おばゆり、ぜんまい、ふきなど、食べられる野草はすべて食べ尽くした。9月になると食べ物は豊富になった。どこでもブドウやコクワがなった。
秋が来たと思っているうちにまもなく冬が襲ってくる。家の中では焚火をぼんぼん燃やして暖をとったが、寒さや雪は遠慮なく押しよせてきて、寝ることもできないまま、夜通し燃やしていることもしばしばあった。この苦しみに耐えかねてか、家族の少い身軽な者は、当時のー戸分ー株30円(※115万3846円)の現金に替えて、網走へ出て行く人もみかけるようになった。
現在残った人々は家族の多い人か、いずれも意志の強い人々で、並大抵のことではない苦悩を嘗めた人々である。[1]
北光社の移民には「独立移住」「補助移住」の2種がありました。
「独立移住」は、移住費150円(※576万9231円)以上を携帯し、渡航費、生活費などは自己資金で賄う2名以上の家族持ちで壮健な者とされました。

心の拠となった北光者事務所兼教会の建物②
「補助移住」は、北光社本社より初年に限り80円(※307万6923円)の給付を受け、30円(※115万3846円)の価格に相当するものを貸与された移民です。文中ではこれらをまとめて概数として100円と言っています。
北光社では、「独立移住」「補助移住」の区別なく初年に1町5反、2年目に2町、3年目に1町5反が給付され、その年の内に開墾を成功させることが義務づけられました。
入植後3年目から「独立移住」は1反につき金66銭7厘、「補助移住」は1円の小作料を本社に納めなければなりませんでした。しかし、これも7年目からは免除されました。
そして入植後9年目に「独立移住」は成功した開墾地の3分の2、「補助移住」は3分の1の所有権を得ることができました。この他に10分の1の薪炭用の土地が付与されました。文中にある「8割開けば大成功とのことで、各戸とも3分の1を開けば所有権を渡す約束」とはこのことでしょう。
また北光社は定款の第1条で「本社は北海道北見国常呂郡クンネップ原野において開墾地の貸し下げを受けし者の合同団体にして、拓殖事業を営むをもって目的とす」と定めています。
入植者は社員=株主であり、500円(※1923万769円)の出資金が1個の投票権となりました。「当時のー戸分ー株30円の現金に替えて、網走へ出て行く」とあるのは、やはり開拓は苦しかったのでしょう。まったく捨て値です。この出資金は7年間年2回の分割払いでした。9年目の土地の分与は社員=株主への配当でもありました。
※現代の貨幣価値に直したものです。週刊朝日編『直段史年表』(1988・朝日新聞社)の「日雇い労働者の賃金・明治29年=26銭を用い、同一労働同一賃金として現代の土木建築労働者の賃金を1万円として換算しています
食える自信がついたのは9年目

大正元年4月、北光社入植団が一応の開拓成功を記念して
撮った記念写真。中央が前田駒次の長男・朝光 ③
嫁を貰うときは「食って行ける見通しが出来たら……」というのが青年仲問の合言葉であった。
どうにか経済的にやって行ける予測の出来たのは入地してから3年目のころで、それまでは「衣度たりて礼節を知る」という言葉があるが、まったくその通りで、生るための見通しが付くか否か夢中だった。
食糧の自給が出来るようになったのはイナキビ、麦類などと栽培してからであるが、麦類は駄目、イナキビ、馬鈴薯でだいたい食べていけると自信のついたのは9年目の頃である。
木下藤吉郎は乾草の上に座りかけ茶碗で三三九度の盃をしたというが、当時は晴れ着1枚もないサッパリした身支度の嫁姿で、ドブロクをイナキビで作り、嫁入りも炉ばたを囲んで行った。
皿もないので、カイベツの葉にイモや魚の煮つけをもって嫁取りのご馳走にした。皿の代用となるホタテ貝殼は網走の浜へ行くといくらもあるが、網走へ行っても、ホタテ貝1枚よりも米1合でも背負って来たかったその頃の苦しさであった。
何はなくとも真に信じあえる人ばかりの心の集い、国と出る頃までに歌っていた知ってるかぎりの歌を唄って喜びとした。
ふけやどんどん、やれ吹けどんどん……とやってはみんな笑わせ、時の過ぎるのも忘れたものである。
(明治)40年頃であったろうか、朝顏のようなラッパのついた蓄音機が部落に見られた。
それッというので部落民一同大いに喜んだが、歌謡も俗曲もあろうはずがない。僅かに教育勅語と訓話が聞とれるくらいのものだった。
「こりやなんだ。太皇陛下とな母ちやんと2人で考えて作ったものだ」
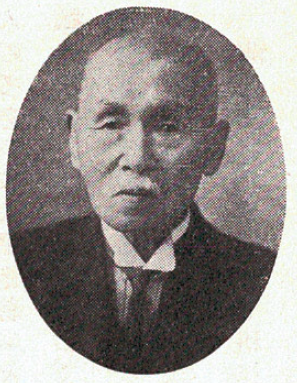
前田駒次④
と一人が云ったら、そばに坐っていた前用駒次翁に「不敬にあたる」とひどく叱られた。[2]
文中の前田駒次は北光社農場の支配人です。社長の坂本直寛は早々に、盟友武市安哉が浦臼の聖園農場に、急死した安哉の代わりに農場を経営するため浦臼に移ったため、代わりに聖園農場から招かれました。やはり土佐士族の出身です。
駒次は文中にもあるように良き指導者として農場を監督し、15年間に実に373町歩の開墾に成功しました。大正6(1917)年に北光社農場は黒田四郎に売却されることで終止符を打ちますが、駒次はそのまま北見に定着し、明治40(1907)年から道議会議員として活躍するなど、北見の発展に大きく貢献しました。
【引用参照出典】
[1]『北見市史』1957・355-361P
[2]同上362−365p
①『北見市史』1957・307P
②同上285p
③同上312p
④同上316p