明治天皇の北海道開拓 (二)

明治天皇肖像①
北門鎖鑰の樹立
明治の開始とともに始まった北海道開拓ですが、榎本武揚率いる旧幕府軍が箱館に上陸したことで足止めされます。北海道開拓に意欲を燃やした清水谷公は戦争の責任を問われて更迭。鍋島正直がいったん開拓使長官につきますが、すぐに東久世通礼と代わります。背景には北方に迫るロシアの影がありました。
■箱館戦争後の一大革新
この乱のまさに平定せんとするや、明治二年五月、明治天皇は重ねて蝦夷地開拓の儀を御下問あらせられ、乱の平定を期として一大革新をなさしめ給はんとの宏謨(こうぼ=国家の大計)を御示しあらせられた。
明治元(1868)年9月20日、榎本武揚率いる旧幕府軍が箱館に上陸すると、清水谷公は防御隊の福山・大野藩兵に出撃を命じますが、旧幕軍の勢いを抑えることができず、清水谷公は寡兵をもって箱館を防御できないと判断して、青森に退避しました。
箱館戦争が収まった明治2(1869)年5月21日、明治天皇は、戊辰戦争の鎮定をうけた今後の国家のあり方として、午前中に五等以上の行政官を召見し、午後には有力公卿、藩主を呼び出して、「皇道興隆」「知藩事選任」「蝦夷地開拓」の三件について勅問されました。
「皇道興隆」は日本の今後のあり方、「知藩事選任」は藩政から近代的な地方自治への転換をはかるものであり、いずれも明治日本を今後どうするかという根源的な問でした。そうしたなかに「蝦夷地開拓」が入っていたことは、いかに明治天皇が北海道開拓を重視していたかを示します。
■開拓督務・鍋島直正
かくして二年六月、兵馬全く収まるに当たって議定鍋島直正を開拓督務に任命せられ、
詔 蝦夷開拓ハ皇威隆替ノ関スル所、一日モ忽(ゆるが)ニス可ラス。汝直正深ク国家重ヲ荷ヒ身ヲ以テ之二任セン事を請フ。ソノ憂国齊民ノ至情、朕嘉納二堪ヘス。独恐ル汝高年遽ニ殊方二赴ク事ヲ。然レトモ朕之ヲ汝二委ス。始テ北頥ノ憂ナカラン。仍テ督務ヲ命ス。他日皇威ヲ北疆二宣ル、汝方寸ノ間ニアルノミ。汝直正懋かな。
の優詔を賜はり、ここに開拓の基礎が定まったのてある。
明治元(1868)年に仁和寺宮嘉彰親王を総督とする蝦夷地統治体制が発足していましたが、やすやすと蝦夷地を反乱軍に明け渡してしまった責任は問われなければなりませんでした。明治2(1869)年6月4日、あらたに議定中納言・鍋島直正が蝦夷地督務に任命されます。明治天皇が鍋島におくった勅書は
蝦夷地開拓は、天皇の権威にかかわるところであり、一日の揺るがすことはできない。なんじ鍋島直正は国家の重荷を背負い、身を持ってこの任務にあたることを自ら志願した。その国を思い、民を思う気持ちを朕は喜びに堪えない。ただひとつ恐れるのは、なんじが高齢にもかかわらず急に遠方に赴くことである。しかし、朕はこの任務をなんじに委ねることで、はじめて北方の脅威に憂いが無くなるに違いない。よってなんじに督務を命じる。天皇の権威を北方に響かせるのは時間の問題である。それを行うのはなんじ直正である。
と書かれていました。明治天皇の北海道に対する高い関心と、鍋島直正への強い信頼が示されています。
鍋島直正は、佐賀藩10代藩主で蘭学をよく学んだ開明派の大名として知られていました。大藩の当主でありながら幕末政局では幕府と距離を置き、戊辰戦争では新政府軍側に立って参戦しています。嘉彰親王に代わる新体制の首領に自ら名乗りを上げました。
鍋島直正が任命されるとと同時に、島義勇、桜井慎平が判官に任命されるとともに松浦武四郎が開拓御用掛に任命されました。
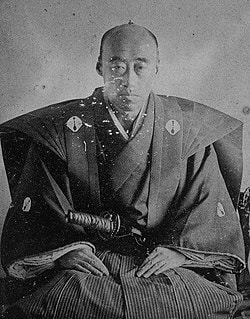
鍋島直正②
■開拓使の設置と東久世通礼
次いで八月には、かの文久の政変における七卿落の一人東久世通礼が開拓使長官に任命せらるるや、畏れおおくも再び優渥なる御沙汰書を拝したのであった。
北海道開拓は皇威隆替之所係、方今至重の急務に候。今般彼地へ出張、数百里外殊方之寒疆に、その事務を管督候事、不容易艱難、一入被思食候。就いては向後、土地開墾、人民蕃殖、北門之鎖鑰厳に樹立し、皇威御更張之基と可あいなり様、勉励尽力可シこれあり旨、御沙汰候事。
同時に開拓判官以下のものにも有難き御沙汰を賜はった。鍋島督務への御詔書、東久世長官への御沙汰書を拝しても、北海道開拓に対する深き御聖慮の程を拝祭し奉る事が出来る。
明治2(1869)年6月17日、明治新政府は版籍奉還を要請し、幕府や旧藩の領地を天皇に返還させ、中央集権体制を固めます。合わせて大蔵省、文部省など省を設置し、官僚組織を整えました。そして、北海道を新たに統治する機関として「開拓使」が設けられました。
そして鍋島正直監務が初代開拓使長官に就く方向で調整が図れましたが、幕末から維新の混乱に乗じてロシアが南下の勢いを高めると、ロシアとの間で国境を画定する交渉が必要となり、病気を抱えていた鍋島正直で良いのか? という議論が新政府内で上がります。
8月に入り、新政府の実力者、大久保利通は自らロシアとの交渉役に当たりたいとの建言書を提出。これは認められませんでしたが、代わりに東久世通礼の名前が挙がり、8月25日に就任しました。
東久世通礼は急進的な攘夷を主張して文久3(1863)年に京都から追放された「七卿落ち」の一人。王政復古によって復権を果たし、外国事務総督として外交問題を担当しました。表向きは鍋島正直の病気による開拓使長官辞任による後退でしたが、実際には対ロシア交渉をにらんだトップの交代でした。この東久世に体して明治天皇は次のような意味の勅書をおくっています。
北海道開拓の成功に皇威のゆくえがかかっている。現在もっとも重要で急を要する課題である。今、かの地に出張し、数百里四方極寒の地において、その事務を総監することは、容易に為しがたい艱難であると思う。ついては、土地を拓き、人民を増やして、日本の北方の防備を固め、皇威のさらなる伸張をあい図るよう努力することを命じる。
明治2(1869)年に鍋島におくった勅書と比べるとより対ロシアをにらんだ北方防衛を意識したものとなりました。

東久世通礼③
■ケプロンへの期待
この外開拓使顧問として招聘せられたホラシ・ケプロンに対し吹上御苑において拝謁を賜はり、
朕汝ヲ欣慕シ、遠ク微シテ北海道開拓ノ事務ヲ司ラシム。汝能ク朕カ意ヲ体し、その長官並次官ヲ輔佐シ、協力以テ成功ヲ奏セヨ。之レ朕力大二汝二望ム所ナリ
との詔勅を恭うし、その任充ちてまさに帰国せんとする、再び拝謁、御優諚を賜い、あるいは東京の開拓使官園に明治六年三月、皇太后陛下の行啓、五月、皇后、皇太后両陛下の行啓、八年二月親しく、天皇陛下の御臨幸をも恭うして、洋風農耕の実習、天覧を賜はる等、皇室の北海道開拓に大御心を垂れさせ給うこと、かくも深きを拝する事はまことに恐懼の至てあって、道民たるもの奮励もって開拓に努力し、一意、聖旨に副い奉らん事を期すべく、我が国民たるものは、またひとしく北海道拓殖の重要性を認識し、北海道拓殖に協力し、もって聖旨に対へ奉らなければならないのてある。
カラフトでの国境画定をめぐるロシアとの交渉については、開拓使次官黒田清隆があたりました。明治3(1870)年7月にカラフトにわたった黒田は、現地で想像以上にロシアが樺太に浸透していること、日本とロシアとの国力の差に、樺太を放棄して北海道開拓に国力を集中させることを決意します。
そして北海道開拓のスピードを上げるためには外国の知識と経験が必要として、明治4(1871)年1月、新大陸開拓の経験のあったアメリカに渡り、グランド大統領に面会。開拓使顧問の派遣を要請しました。グランド大統領は黒田の要請に応え、農務長官の席にあったホーレス・ケプロンを顧問として赴任させることを約束します。
この決定をことのほか、喜んだのが明治天皇でした。天皇はケプロンに対して次のような勅書をおくります。
朕、なんじを迎えることを喜び慕い、北海道開拓の事務をまかせる。なんじはよく朕の思いを体し、開拓使の長官や次官を補佐し協力して北海道開拓を成功させよ。これが朕が大いに望むところである。
ケプロンは明治8(1875)年5月に帰国しますが、このときも明治天皇はケプロンにあってねぎらいの言葉をかけました。明治新政府の確立という大事なときにもかかわらず、東京にあった開拓使の官園を訪れるなど、たえず北海道開拓の進捗に強い関心を寄せていました。
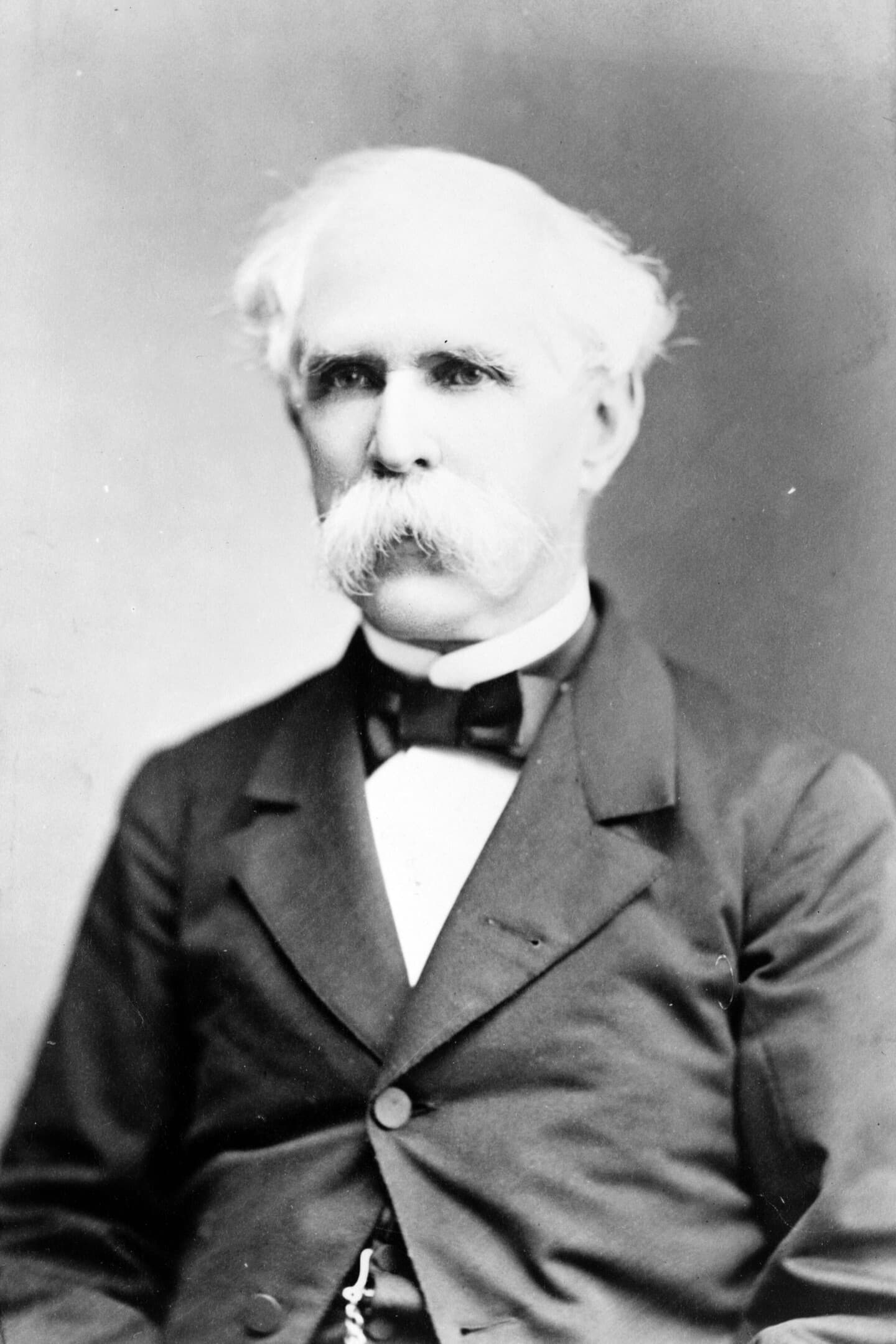
ケプロン④
【引用文献】
『開道七十年』1938・北海道庁・8~9p
①明治神宮>明治院宮とは https://www.meijijingu.or.jp/about/
②③④ウイキペディア
























